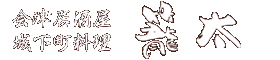|會津武家料理|

会津藩が饗応に用いた「會津武家料理」を 現代にもお楽しみいただけるようにご用意いたしました。
1日1組限定(2人以上6人まで)
おひとり様 5,000円(税込 飲み物別途)
※電話で予約してください。
0242-32-5380( 受付時間 14:00-20:00 )
|献立例|
※時節により換わる品がございます
本 膳
- ⼋⼨…揚卵 茗荷酢漬 茸おろし 薬⽤⼈参の漬け揚げ ⽴川⽜蒡の胡⿇煮
- 膾…鯉の洗い
- 坪…菊の酢の物
- 鉢…鰊の⼭椒漬
- 粕汁
- 飯
- ⾹の物…⽠の奈良漬・⾚蕪漬け・三五⼋漬
⼆の膳
- ⼤平…煮〆
- 岩⿂⼭椒煮
- こづゆ
會津武家料理とは
「會津武家料理」とは、昭和60年代の古文書調査により明らかになった、会津藩の記録に残された饗応料理のことです。
会津藩の武家の学問所・会津藩校日新館にて伝授された礼式方の作法に基づき、主に川魚や乾物、伝統野菜を用いた非常にレベルの高い料理だったことが分かり、追加調査において膨大な記録が発見されたことで、全容が次第に明らかになってきたものです。
その古文書調査に関わり料理復元の中心となったのが、懐石料理「ふくまん」で知られた当店亭主の鈴木真也です。

礼式方とは
では、いつごろから会津の地に礼式が伝わってきたのでしょうか。
藩政時代からさかのぼること戦国時代末期に、武田信玄との合戦に敗れ逃れてきた信濃林城主の小笠原長時が、越後を経て蘆名氏が治める会津に在住しておりました。
のちに徳川幕府の礼式として採用された「小笠原流礼法」として知られる小笠原家に連なる人物です。
長時は会津で弓や馬術のほかに、殿中の様々な作法を伝えていたものと思われますが、その中に献方と呼ばれる食事作法があったことがわかっています。
時代を経て、会津藩校日新館が設立されるに至り、その教義の中に採用され、やがては民間にも普及していったことは町方に伝わる古文書からも見えてきています。
その教義は口伝や記述などさまざまな方法で会津地方に広く伝授され、礼法の「形」は昭和40年代まで主に南会津にも遺されておりました。

会津絵のうつわ
八寸を饗する漆器には「会津絵」と呼ばれる模様が描かれております。
産地として400年以上の歴史を持つ会津ではさまざまな漆器が作られており、独自の技術も生み出されてきました。そのなかでも「会津絵」は金箔を用い、松竹梅や破魔矢などを賑やかにあしらった会津独自の意匠です。江戸後期にはいまに近いスタイルに整い、往時は茶懐石や本膳料理の吸物椀として用いられたと考えられているようです。めでたい吉祥柄はもてなしの席で大いに重宝されたのではないでしょうか。